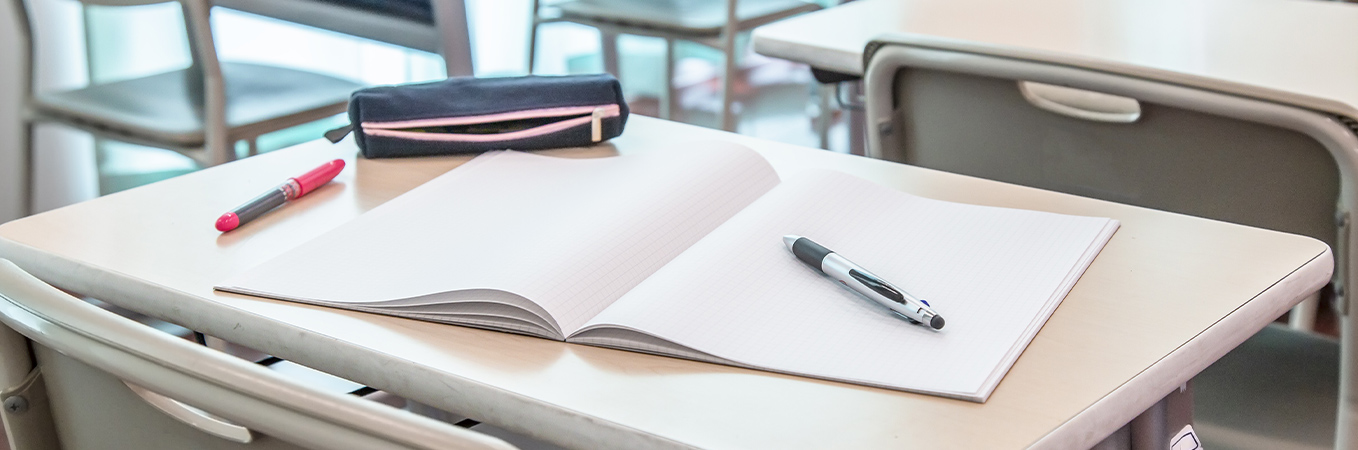こんにちは。都立入試解説の第2弾は社会。
ここ数年4つの国や都道府県を4つの選択肢に一致させる完全解答の問題が増加し、受験生を苦しめています。
大問ごとに見ていきましょう。
第問1 小問集合
3分野からの小問ですが例年通りの形式、難易度です。問1はルートマップの北の方角に注目すれば地形図と照合できたはず。問3は国からの依存財源のうち、国庫支出金は用途が決まっているもの、地方交付税交付金は用途は自治体の任意です。
大問2 世界地理
形式、難易度ともに平年並み。雨温図はさんざん対策しましたね。問3は与えられた情報からフランスとイギリスに絞り、そこからはやや難しかったかも。「航空機産業」や「北部にある首都」かフランスに絞り込めます。
大問3 日本地理
ここも平年並みでした。記述問題は避けたがる受験生が少なからずいますが、「何を問われているか」「どの資料の何に注目するよう指示されているか」に忠実に考えれば難しくありません。今年も解答しやすい問題でした。
大問4 歴史
美術史を切り口に構成された問題でしたが、やるべきことは「時代の順番を覚える」と「用語・人名を時代ごとに分類する」こと。ただし問2は江戸時代に該当する選択肢が2つあり、菱川師宣→元禄文化、喜多川歌麿→化政文化までさらに細分化して整理しておく必要がありました。
大問5 公民
他の分野より知識の範囲が限定的で、かつ中3で学習したばかりともあって、取り組みやすい分野です。例年通り知識だけで解ける問題が多いです。問3は経済成長率の推移のグラフを読み取り、好況から不況へ転じるときの財政政策、金融政策の組み合わせを選択するものでした。丸暗記しても良いですが、「景気が良い」=「市場にお金がたくさん流通する」という本質が理解できていればそれだけで解けるはずですね。
大問6 分野融合
都立の大問6は“3分野融合”と言われながらも実質的には世界地理と歴史のやや難しい追加問題なイメージ。取り組み方はそれぞれの分野と同じアプローチで良いと思います。問2は「イギリスからの独立」という点でエジプトとオーストラリアの2択ですが、経済成長率推移の資料の読み取りからエジプトになります。
全体を通してみると、難問と言える難問はなく、過去問を演習した上で各分野に対する対策が準備できた受験生は得点できた問題が多かったのではないでしょうか。